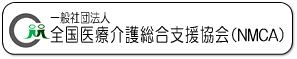サービスのご紹介 ~職員とのトラブル解決~
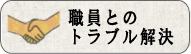
|
職員とのトラブルを未然に防ぐには、まずは就業規則の見直しが有効です。10名未満なので作成義務はないと思われる方も多いのですが、就業規則は自院を守るためでもあるのです。 ここでは、労使トラブルの実例をご紹介いたします。 |
|---|
就業規則で防げるトラブル事例
![]() 事例2:休職を繰り返す職員を辞めさせたいが…
事例2:休職を繰り返す職員を辞めさせたいが…
![]() 事例3:時間外労働について、未払い残業として約680名の看護師に、
事例3:時間外労働について、未払い残業として約680名の看護師に、
計1億円近くの支払いを命じられた
![]() 事例4:合意退職のはずが、不当解雇との連絡が…!?
事例4:合意退職のはずが、不当解雇との連絡が…!?
事例1:パート職員から退職金を要求された!
|
介護施設YのパートJさんが退職したいという話が、所属長経由で総務部に届きました。 特に問題もなく、退職手続きが完了しようとしていたところ、 Jさんから総務部に、 「退職金の支払いはいつか?」との質問がありました。 施設Yの就業規則には、継続して5年以上勤務した職員が退職する場合に退職金を支給するという規程があります。 これに対してJさんは、 |
この結果として、施設YはJさんから退職金の申請を拒否することはできませんでした。
就業規則は、その対象範囲を明確にしておかないと、上記のようなトラブルが起こります。
退職金だけでなく賞与なども、アルバイトやパートタイマーに支給しなければならなくなった、というケースが少なくありません。
私たちが健康診断を受けるように、就業規則も現状に合わせ、労務管理リスクが潜んでいないかどうかを定期的に確認する「健診」が必要になっています。
事例2:休職を繰り返す職員を辞めさせたいが…
|
介護施設Y(入所定員100名、職員110人、開設7年目)に勤務しているHさんは、 半年ほど前より休みがちになりました。 そして2ヶ月ほど後、専門医より「うつ病」と診断され休職していました。 その後、ようやく回復し復職したのですが、復職後3週間でうつ病が再発したとのことで、再度休職に入ってしまいました。その後も復職しては再発を繰り返す日々が続きました。 他の職員へ影響が出ていることに気付いた社長は、Hさんの解雇を決意したのです。 そこでHさんに次のように伝えました。 Hさんはこれに対し、 そして、これがきっかけとなりその後のトラブルへと発展したのです。 |
介護施設Yの休職規程には、Hさんの言う通り休職の通算には規程がありませんでした。
その結果、社長はHさんを解雇することはできませんでした。
事例3:過去の時間外労働について、未払い残業の多額支払いを命じられた
|
・T病院にて、新人看護師の職場での自己学習や、緊急の患者対応、後輩指導等の時間に値する残業代の未払いがあったとして、 看護師約680名に対して、約1億4,350万円の支払いを命じられた。 ・就業規則に「所定労働時間(7時間30分)超に対し、時間外手当の支給を行う」旨の規定があったため、職員約100名へ過去の未払い代として、総額600万円程度の支払いを命じられた。 |
未払い残業問題で意外に多いのが、
事業主側が、法律や規定を誤って理解してしまい、支給していないケースです。
後者の事例では、就業規則の所定労働時間(7時間30分)超に対し、時間外手当の支給という規定を、法定労働時間(8時間)超からの支給と勘違いし、長年8時間超に対し、時間外手当の支給を行っていました。
ある時、些細なことからそのことが公になってしまい、職員約100名へ30分間の差額分の
時間外手当を支給することになってしまったのです。
1日30分の時間ではありますが、総額600万円程度の支払い程度にはなってしまいました。
従って、このような事態にならない様に、法律や規定を正しく理解する必要があるのです。
事例4:合意退職のはずが…
|
K病院では、医事課のHさんと話し合いの末、10月末での退職ということで話を進めていました。 いわゆる退職勧奨です。病院側は事務長がHさんに十分理解して頂いたと思い、 特にHさんの退職に関して何ら不安を感じていませんでした。 ところが、ある日のこと、労働基準監督署から連絡がありました。 事務長は理由がわからず、Hさんは自己都合退職ということで辞めて頂いた、 |
労働局や労働基準監督署によせられる相談の中で、最も多い相談が「解雇」に関する内容です。
事例では、労使の話がスムーズに済んだかに思われましたが、Hさんがその後になって、
労働局や労働基準監督署に相談し、考え方を一転させてしまったのです。
この様なケースは決して珍しくありません。
通常、退職の際は本人より退職届を提出してもらうのが一般的です。
しかし、これだけでは不十分です。職員が病院側から半強制的に提出を求められた、と訴えられることもあるのです。
特に退職勧奨は行き過ぎた行為があった場合は、不当解雇とみなされるケースもあります。
従って退職届とは別に、合意退職に相違ない旨の覚書を本人から提出してもらうことが対応策となります。


 三塚 浩二
三塚 浩二